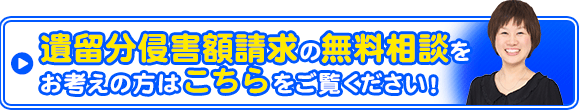遺留分侵害額請求の時効に関するQ&A
遺留分侵害額請求には、時効があるのですか?
多くの請求権と同じく、遺留分侵害額請求には期限があります。
遺留分侵害額請求の時効は、1年と10年の2種類があります。
1年の期限の内容は、どのようなものですか?
1年以内に遺留分の請求をしないと、遺留分の権利は時効によって消滅するという制度です。
遺留分侵害額請求の1年の期限は、いつを基準に考えるのですか?
「相続の開始」と「遺留分の侵害」の両方を知った時を基準にします。
「相続の開始」とは、ご家族が亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った時を指します。
「遺留分の侵害」とは、遺言書に特定の相続人に多額の遺産を相続させる旨の記載がある結果、他の相続人が遺留分以下の遺産しかもらえないというような事態を指します。
「相続の開始」と「遺留分の侵害」の両方を知った時から、1年のカウントがスタートします。
例えば、ご家族が亡くなったことを知ったとしても、遺言書の存在を知らなければ、遺留分の侵害を知らないという事態もあり得ます。
このようなケースでは、1年の期限はまだスタートしません。
10年の期限とは、どのような内容ですか?
「相続の開始」から10年が経過した場合、遺留分の権利が消滅するという制度です。
仮に、ご家族が亡くなったことを知らなかったとしても、10年が経過すれば、遺留分侵害額請求ができなくなります。
遺留分侵害額請求が時効にならないためには、どうすればいいですか?
期限内に、遺留分侵害額請求を行う必要があります。
いったん、遺留分の請求をする意思表示をすれば、少なくとも1年の期限はクリアできます。
そのため、ひとまず遺留分の請求をして、遺留分の権利が時効になってしまうことを防いでから、交渉を進めることになります。
遺留分の請求は口頭で伝えればいいですか?
口頭で伝えた場合、遺留分の請求を行ったという証拠が残りません。
「遺留分の請求を受けたことはない」と主張されないように、証拠に残る形で、遺留分の請求を行う必要があります。
もっとも簡単で一般的な方法が「内容証明郵便」ですので、原則として内容証明郵便を使い、証拠を残しておくことをおすすめします。
参考リンク:郵便局・内容証明
遺留分と生前贈与に関するQ&A 相続放棄の手続きに関するQ&A