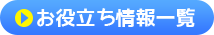相続手続き
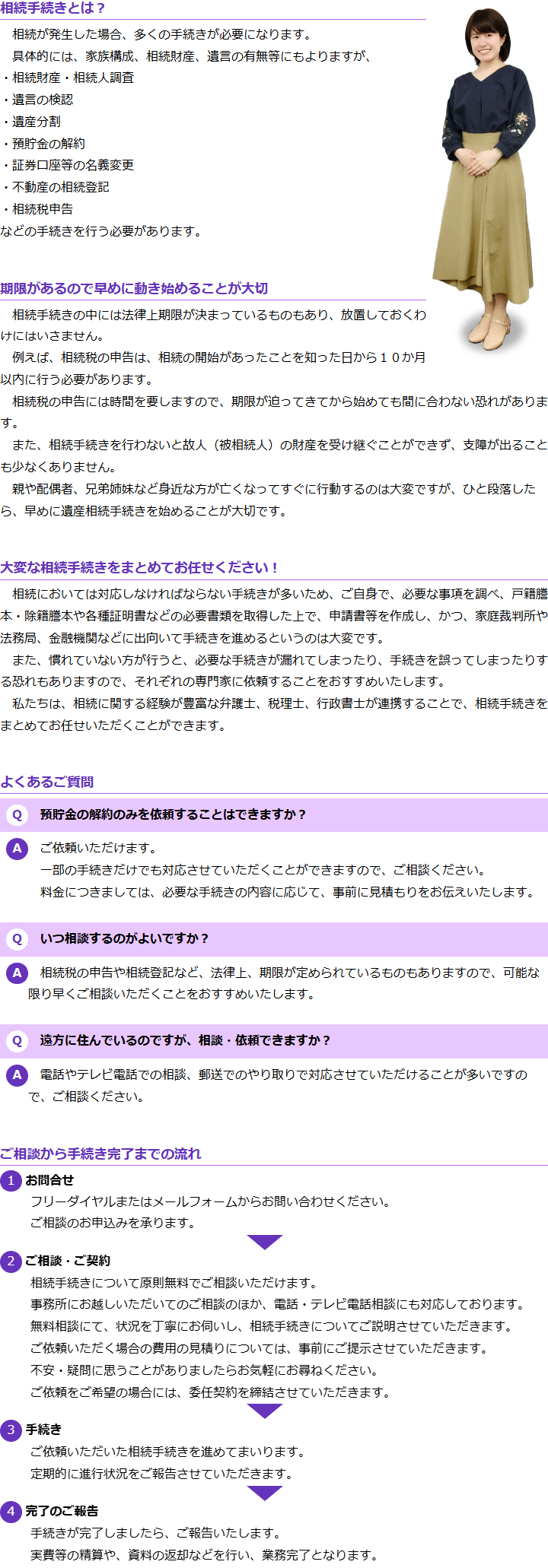
相続手続きは誰に依頼するか
1 相続財産・相続人調査

相続財産調査は、相続人からの委任を受けて、各金融機関や市区町村、各団体に対して被相続人が所有していた財産(金融資産や不動産、債務等)について問い合わせを行います。
相続人調査は、市区町村が管理する戸籍を調査し、被相続人の親族関係を把握することで、誰が相続人となるかについて調査いたします。
また、相続人間で付き合いのない人もいますので、そのような場合の所在調査を行う場合もあります。
このとおり、相続財産・相続人調査は、相続手続きを行う上での土台となる調査ですので、相続手続きを依頼する行政書士、司法書士、税理士、弁護士といった専門家であれば委任状を取得した上で、執り行うことができますので、相続手続きを依頼する専門家にそのまま依頼することが多いです。
2 遺言の検認
遺言書の中でも、自筆証書遺言書(遺言者が自分の手で書き上げ、作成した遺言書)の場合は、家庭裁判所で検認という手続きを行うことで、裁判官による遺言書の確認作業を行う必要があります。
この手続きのためには、家庭裁判所へ検認の申立てを行います。
裁判所への提出書面の作成になりますので、検認の手続きを専門家に依頼して行う場合は、司法書士か弁護士に依頼する必要があります。
3 遺産分割(遺産分割協議書の作成)
相続手続きを行ううえで、被相続人の財産についてどのように分割するか(どの財産を誰が取得するか)について相続人全員で協議を行い、その協議内容を遺産分割協議書という形でまとめる必要があります。
分割内容を書面にまとめて証明する書面を作成することは、行政書士、司法書士、税理士、弁護士といった専門家において行うことが可能です。
その遺産分割協議書を用いて行う手続きに必要な情報が記載されるようにその専門家によって作成されます。
ただし、遺産分割協議前にどう分けるかについて争いがあるときに内容をまとめる場合、原則、弁護士しかできません。
4 預貯金の解約・証券口座等の名義変更
預貯金の解約や証券口座等の名義変更については、専門家は遺産分割協議の内容に従い、相続人からの委任状を用いて手続きを行うことができます。
そのため、上記の書面があれば、行政書士、司法書士、税理士、弁護士が手続きを行うことが可能です。
一般には、遺産分割協議書の作成を行った専門家にそのまま依頼することになります。
5 不動産の相続登記
不動産の相続登記は、その不動産の所在地を管轄する法務局に対して申請を行うことで手続きを行います。
相続登記を行うのは、主に司法書士になりますが、弁護士も手続きを行うことが可能です。
相続登記を行う場合は、管轄する法務局によって取り扱いが異なるものもありますので、その手続きを行う法務局に慣れている、その法務局所在地で主に活動を行っている専門家に依頼される方が手続きをスムーズに進めることができる場合が多いです。
6 相続税申告
被相続人が一定額以上の財産を有していた場合、財産を相続した相続人は、期限までに被相続人の最後の所在地を管轄する税務署に対し、申告と必要であれば納税まで行う必要があります。
この申告業務を依頼することができるのは、税理士のみとなります。
ある程度の財産をお持ちの方が亡くなり、相続税の申告が必要か確認をしたい場合は税理士に相談することになります。
相続税の申告には期限がありますので、お早めに相談をされるのがいいでしょう。